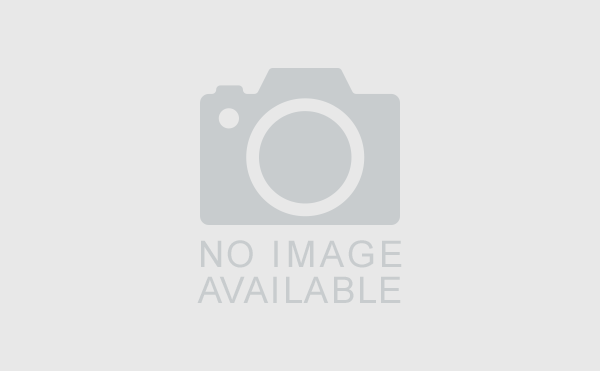⭐【第3弾】令和9年度埼玉県公立高校入試情報
令和9年度埼玉県公立高校入試についての第3弾です。
8月29日付で,県教委から面接試験についてのリーフレットが発表になりました。
このリーフレットでは,主に面接試験についての説明がされていますが,一部,こちらも新しく導入される『自己評価資料』についての説明もあります。
まずは面接について詳しく見ていきましょう。
≪面接の実施概要について≫
①面接試験は学力検査(筆記試験)の翌日に実施。
例えば,令和9年度入試の日程だと,
・2月25日;学力検査(筆記試験)
・2月26日;面接
となります。
実技などの特色選抜をする学校・学科については,面接の翌日に特色選抜を行う場合もあります。
※前々回のレポートでお伝えした通りです。
②面接の形式は高校によって異なる。
個人面接,集団面接のどちらの形式で面接試験を実施するかは高校によって異なります。
詳細は,各高校の『選抜実施内容』で確認することができます。
令和7年12月に暫定版,令和8年5月に確定版が公表される予定です。
③面接時間は一人当たり最長10分程度。
面接は,以下のような流れになります。
・入室
↓
・My Voice(マイ ボイス);1分半~2分
↓
・質問/応答;3分半~6分
↓
・退室
入退室の時間を含めると,一人当たりの面接時間は最長で10分程度になります。
※My Voiceについては後述。
《面接の内容について》
①My Voice(マイ ボイス)
中学校生活や学校外での活動を振り返ったり,自らの経験や将来への思いを伝えたり,受検生が話をする,いわば『自己PR』です。
面接の一番最初に設けられます。
②質問/応答
受検生がMy Voiceで話した内容に対して,面接官の先生(2人以上)が質問をし,それに受検生が答えていく時間です。
いわゆる『面接』の部分です。
《評価について》
①評価の観点は3つ。
面接の評価は『主体的・協働的な学びの力』『自らの人生や社会を切り拓く力』という全校共通の観点に,各高校が独自に定めた観点を加えた,3つの観点を評価します。
話の上手さや正確さは評価の対象ではありません。また,これまでの活動や取り組みの実績そのものが評価されるのではなく,実績に至るまでの過程や意欲,身に付いた力、学びに向かう力などが多面的に評価されます。
話の上手さや内容は評価されませんが,言葉遣いなどの最低限のマナーは身につけておく方が良いと思います。
②評価は3段階。
①の3つの観点を『5・4・3』の3段階で評価します。
5…大変優れていると評価できる,4…優れていると評価できる,3…評価に値する
の3段階を基本とします。
全員が一律で3を持っていて,面接の内容によって,4,5と上がっていくというイメージかと思われます。
以上が面接試験についてのまとめです。
事前にガチガチに面接練習をしておくよりも,My Voiceで話す内容を大まかに考え準備しておいて,それについてのいろいろな質問に対して自分の言葉で答えられるように,My Voiceの内容を深く考えておくと良いのではないでしょうか。
なお,緘黙などの場合は,中学校の先生を通じて高校に相談しておいてください。
今回,発表されたリーフレットには,一部,『自己評価資料』についての記載があります。
自己評価資料とは,令和9年度入試から導入される自己PRの資料,ポートフォリオです。
紙面の上1/4は氏名や中学校名などの欄となっていて,中段1/2が自己評価資料のメインの部分,下の1/4が学校独自項目となります。(※リーフレットの画像を参照してください。)
自己評価資料は面接を行う際の補助的な資料で,委員会活動や部活動,資格など,学校内外での活動やその意欲などを,自分の言葉で記入した資料です。
得点の算出には使用されません。もちろん,文章の上手い下手や多い少ない,文字の上手い下手も評価の対象になりません。
自己評価資料の記載の中でちょっと着目していただきたいのが,自己評価資料の紙面の下1/4にある『学校独自項目』の部分です。
この学校独自項目については,リーフレットに以下のような記載があります。
[以下抜粋]
受検生は、志願する高校が「選抜実施内容」の面接の欄に「学校独自項目」を設定している場合は、その項目の内容について記載してください。
各高校では、「学校独自項目」についても評価の観点及び評価規準を定めて、得点を算出します。
[以上抜粋]
自己評価資料のメインとなる部分は面接の資料として使用され得点化はされませんが,一部,学校独自項目を設定した学校については,この部分を点数にすることも考えられそうです。
ただ,基本的に現在の中2以下の生徒が受験に向けてすることは,今までと大きく変更はないと言えるでしょう。
学校の授業をしっかり受けてテストの点数もちゃんととる。
部活や課外活動,資格取得などに打ち込む。
まずは日々,できるところから真剣に取り組むようにしましょう。
それにしても,ココ1ヶ月くらいで新しい入試が一気に具体的になり,発表されていますね。
前回も書いたことですが,ネットなどのうわさ話で不安にならないようにして,できるだけ正確な情報を得られるように,アンテナ感度をよくしておく必要がありそうです。